
遺留分侵害額請求には、相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から「1年間」、または相続開始の時から「10年間」の時効があります。権利を失わないために何をすればよいのかとともに、遺留分侵害額を計算するうえで問題になる生前贈与の期間についても解説します。
遺留分とは何か?

遺留分とは、亡くなった被相続人の財産について、一定の範囲の法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人が、例えば、「自分の財産は全て長男に取得させたい」と考えて、その旨の遺言書を作成していたとしても、他の相続人の有する遺留分を奪うことはできません。
このため、上記のような遺言書が作成されていた場合、配偶者や次男など他の相続人は、遺産を全て取得した長男に対して、遺留分に相当する金銭を支払うよう請求することができます(これを、遺留分侵害額請求と言います)。
遺留分を請求できるのは誰か?
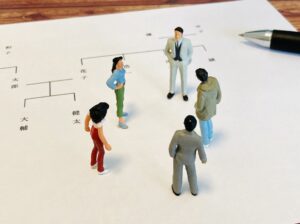
遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子(子が既に死亡している場合は孫など)、直系尊属(親など)です。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹は、相続人になる可能性はあっても、遺留分はなく、遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合は?

遺留分の割合は、遺留分を算定するための価額(被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+生前贈与した財産の価額-被相続人の債務額)に、次の割合をかけたものです。
①直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
②それ以外の場合 2分の1
相続人が複数いる場合には、上記で出した金額に、さらにその者の法定相続分をかけて計算します。
例えば、遺留分を算定するための価額が3000万円で、相続人が配偶者と子2人というケースで、子1人あたりの遺留分は、
3000万円×2分の1×4分の1=375万円
となります。
遺留分侵害額請求権には時効がある!

このように相続人に最低限の取り分を保障する遺留分ですが、遺留分侵害額請求権の行使には時効があります。
時効期間は、
①相続の開始(=被相続人が亡くなったこと)及び遺留分侵害の事実(=遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと)を知った時から「1年」
または、
②相続開始の時から「10年」
です。
①相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から「1年」
この場合の時効期間は「1年」と、大変短くなっています。
被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分の遺留分を侵害するような生前贈与や遺言書の存在が明らかになった場合には、その時点からたったの「1年」で遺留分侵害額請求権は時効消滅してしまうのです。
親族が亡くなった直後の悲しみの中、お葬儀の手配や役所関係の諸々の届出、相続税の申告・納税手続きなど、やらなければならないことが沢山ある中では、うっかりすると「1年」など、あっという間に過ぎてしまいます。
遺留分を請求することを考えている場合で、この①に該当する場合には、「1年」以内に権利を行使するように注意しなければなりません。
②相続開始の時から「10年」
遺留分侵害額請求権は、①の場合だけではなく、相続開始の時(=被相続人が亡くなった時)から「10年」が経過することによっても、時効により消滅します。
この場合は、相続人が、被相続人が亡くなったことを知っていたかどうか、自分の遺留分を侵害するような生前贈与や遺言書が存在することを知っていたかどうかは、関係がありません。
そのような個々の相続人の認識に関わらず、相続開始(=被相続人の死亡)という客観的事実を基準に、そこから「10年」を経過することによって、以後、遺留分の請求はできなくなる、というものです。
遺留分侵害額請求権の行使方法

それでは、「1年」ないし「10年」の消滅時効にかかる前に、どのように遺留分侵害額請求権を行使したらよいのでしょうか?
具体的にどのような方法によるべきか?
実は、法律上、遺留分侵害額請求権の行使方法についての定めはありません。
そのため、例えば、相手方(遺留分を侵害している人)に対し、口頭で「遺留分を請求します」と伝えるだけでも、遺留分侵害額請求権を有効に行使したことになるのです。
もっとも、上記のように口頭で意思表示するだけでは形に残りませんし、後々、遺留分侵害額請求権が時効消滅しているのではないかが争いになった時に、期間内にきちんと請求権を行使したことを証明する手立てがなく、不安です。
そこで、実務上は、配達証明付き内容証明郵便を用いるのが一般的です。
配達証明付き内容証明郵便を使用すれば、いつ、どのような内容の書面を発信し、相手方がいつその書面を受領したかが分かりますので、「●年●月●日付けで遺留分侵害額請求をしたこと、相手方が●年●月●日にその書面を受領したこと」が証明できます。
なお、内容証明郵便には、請求する遺留分の具体的な金額まで書く必要はなく、遺留分侵害額請求をする意思が明確に表示されていれば、それで足ります。
内容証明郵便を送った後はどうする?
このように、「1年」ないし「10年」の期間内に内容証明郵便を送付すれば、ひとまず、遺留分侵害額請求権を保全したことになります。
その後は、通常であれば、内容証明郵便を受け取った相手方から何らかのアクション、例えば、「そちらに支払うべき遺留分について、話し合いをしたい」等の連絡が返ってくるでしょう。
そこで、話し合いを進め、その中で遺産目録の開示等も受けながら、遺留分の金額を確定し、支払い方法などを決めていくことになります。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を起こして裁判所で話し合いをします。
調停でもまとまらない場合は、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起することになります。
このように、当事者間での話し合い→調停→訴訟の順番です。
遺留分の計算に関わるその他の期間制限

さて、遺留分については、権利行使の期間制限の他にも、遺留分侵害額それ自体を計算する際に、期間が関わってくるものがあります。
それは、特別受益や生前贈与につき、何年前のものまで遡って計算に含めないといけないのか、ということです。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額の計算方法は、
遺留分(②)-権利者が受けた特別受益の額(①)-権利者が相続すべき具体的相続分+権利者が負担すべき相続債務の額
です。
権利者が受けた特別受益の額
上記計算式の、「権利者が受けた特別受益の額(①)」には期間の制限はなく、それが何年前の特別受益であっても、計算に含まれます。
遺留分を計算する際の生前贈与の価額
一方、上記計算式の、「遺留分(②)」では少し事情が違ってきます。
この「遺留分(②)」は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+生前贈与した財産の価額(③)-被相続人の債務額
という計算をして導き出されるのですが、この生前贈与した財産の価額(③)では、
■相続人に対する原則10年以内の生前贈与(特別受益に限る)
■第三者に対する原則1年以内の生前贈与
が含まれます。
(例外的に、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、相続人に対する10年以上前の特別受益も、第三者に対する1年以上前の生前贈与も加算の対象に含まれます)
このように、具体的な遺留分侵害額を計算する際の権利者が受けた特別受益の額と、遺留分算定の基礎となる財産を計算する際の生前贈与の価額とでは、加算すべき生前贈与について、それぞれ期間制限の有無が異なってきますので、注意が必要です。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






