
「パワハラなんてうちの会社では起きていない」「人数が少ないから大丈夫だろう」
こうした認識は、今やリスクそのものです。
2022年4月からは、中小企業にもパワハラ防止措置の義務が課され、「何もしない」は違法行為に当たる可能性すらあります(大企業では2020年6月からパワハラ防止措置が義務化されております)。
本コラムでは、特に中小企業におけるパワハラ防止法の実務対応を中心に、法律の基礎知識から相談窓口の設置方法、現場での注意点まで、実践的な視点で解説します。
「パワハラ防止法」とは何か?

背景と制定の経緯
パワーハラスメントによる精神疾患や退職、損害賠償請求などの問題が社会問題化する中、国は職場のハラスメント防止のため、2019年に労働施策総合推進法を改正しました(通称:パワハラ防止法)。
企業規模により施行時期が分かれていましたが、2022年4月からは中小企業も義務対象となっております。
パワハラの定義(厚労省指針より)
次の3要件をすべて満たすものが、法的に「パワハラ」と認定されます:
- 優越的な関係に基づいて
例:上司から部下、正社員から非正規社員へ等
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
例:人格を否定する暴言、無視、物理的攻撃、過大・過小な業務命令など
- 就業環境を害すること
例:職場での孤立、精神的苦痛、業務遂行が困難になる状態
中小企業の義務となったことの意味
中小企業にとって、「制度対応にコストがかかる」「体制整備に時間がかかる」という課題は現実としてあります。
しかし、対応を怠った場合のリスク(行政指導、損害賠償、風評被害など)はそれ以上に深刻です。
企業が講じるべき「防止措置」の全体像

労働施策総合推進法に基づき、企業は次のような防止措置を講じることが義務付けられています。
(1)事業主の方針等の明確化と周知・啓発
- ハラスメントを許容しない旨の方針を明示
- 相談したことで不利益を受けないことを明確に
- 社内掲示や就業規則・研修資料への明記
(2)相談窓口の設置と適切な対応体制
- 相談受付体制の整備(相談担当者の配置・教育)
- 対応マニュアルの整備と、迅速・適切な対応
(3)再発防止に向けた措置の実施
- 被害者への配慮措置(配置転換、休職対応など)
- 加害者への懲戒や指導
- 関係者への継続的なフォロー
これらはすべて、「就業環境の維持・改善」が目的です。
「一応置いてあるけど機能していない相談窓口」では、義務を果たしたとは見なされないことがあります。
相談窓口の設置方法と実務上の注意点

▷ 社内での設置が原則
- 経営者または人事・総務部門が窓口になるのが一般的です。
- 社内での中立性が確保できない場合は、**外部委託(社労士・顧問弁護士)**の活用も可能です。
▷ 担当者の選任と教育がカギ
窓口担当者には以下のような資質が求められます:
- 被害者・加害者双方に対する中立性
- プライバシーの厳守意識
- ハラスメントの定義や対応フローの理解
- 相談対応の初期教育(厚労省のガイドライン活用も推奨)
▷ 相談内容の記録と対応フロー
- 相談記録(日時・内容・対応策)は必須
- 初動対応の遅れが、被害の拡大や企業責任の発生につながることも
- 匿名相談を認めるルールも一定の効果
違反するとどうなる?未対応のリスク
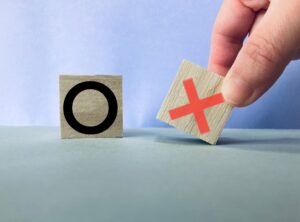
(1)労働局の行政指導対象に
ハラスメント相談対応が不適切であると、労働局から是正指導や報告命令を受けることがあります。重大なケースでは、企業名が公表されることも。
(2)損害賠償リスク
安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反、人格権侵害等により、会社側に数十万~数百万円規模の賠償命令が出された判例も多数存在します。
(3)企業イメージの毀損
一度パワハラ問題が報道やSNS等で広がれば、顧客離れ・採用難・離職率増加という、企業経営全体に関わる悪影響も。
弁護士が活躍する場面

【1】相談窓口の設計・運用支援
相談窓口は設置するだけでは意味がありません。
弁護士が関与することで、以下のような実効性のある体制が整います:
- 社内ルールと整合性のとれた対応マニュアルの作成
- 担当者の教育と研修(守秘義務、聞き取り技術など)
- 被害者・加害者対応の初動フロー作成
- 記録・保存・社内通報体制の整備
特に就業規則との整合性が取れていない場合、相談対応後にトラブルへ発展するリスクが高まるため、制度設計段階からの弁護士関与が極めて有効です。
【2】社内対応における「判断」に関わる場面
相談を受けたとき、「これはハラスメントに該当するのか?」「どう対応すべきか?」は非常にデリケートな判断を要します。
弁護士にアドバイスを求めることで、
- 相談内容が法的にどの程度深刻なのかを判断
- 被害者保護と加害者の権利のバランスを取る
- 必要に応じた懲戒処分の妥当性判断
を、中立的かつ法的に適正な形でアドバイスできます。
【3】トラブル発生時の初動対応(第三者調査・面談など)
仮に深刻なハラスメントが発覚した場合、迅速かつ慎重な対応が必要です。
弁護士が関与していれば、
- 事実関係の調査(ヒアリング・証拠精査)
- 当事者面談の同席・助言
- 第三者委員会的役割
などを通じて、社内だけでは解決が難しい場面で“火消し役”を担うことが期待できます。
【4】損害賠償請求や労働審判・訴訟への備え
近年、ハラスメント被害を理由とする訴訟や労働審判の件数が増加しています。
弁護士が関与していれば、
- 書面対応・交渉を代理できる
- 企業の責任を最小限に抑える防御戦略が取れる
特に「初期対応のまずさ」が原因で訴訟に発展する例が多く、法的リスクを最小限に抑える専門家の助言が不可欠です。
【5】制度整備と定期点検の伴走支援
相談窓口や社内制度は、一度作ったら終わりではありません。
むしろ「定期的に運用を見直すこと」で初めて機能します。
弁護士が継続的に関与することで、
- 法改正や判例変更へのアップデート
- 社内研修・教育のサポート
- 毎年の制度点検と改善提案
といった「制度の持続可能性」が担保されます。
まとめ
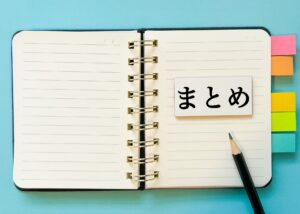
ハラスメント対策は、もはや“対応するかしないか”の問題ではなく、“どう対応するか”の時代です。
- パワハラ防止法により、中小企業も防止措置が義務化
- 相談窓口は、形だけでなく実効性が求められる
- 対応を怠ると、訴訟リスク・行政指導・企業イメージ低下と多方面に波及
- 担当者の教育、記録の整備、迅速な初動対応がカギ
- 防止措置の整備は、「社員の安心」と「企業の信頼」を守る仕組み
企業の信頼性は、制度と実践の積み重ねで築かれます。
経営者・人事担当者は、“やっているつもり”で終わらせず、実態として「対応できているか」を定期的に見直すことが重要です。
弁護士を介入されることで、労務トラブルを未然に防ぐことが期待できます。
顧問契約を行うことで、そうした安心を手に入れることも一つの選択肢かもしれません。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。






