
人の死亡を原因として財産が移転するものには、「相続」、「遺贈」、「死因贈与」があります。本稿では、このうちの「死因贈与」につき、「相続」や「遺贈」との違いから、撤回が認められるかどうかまで、基礎的な事項を弁護士が解説します。
「死因贈与」とは?

「死因贈与」―――あまり聞き慣れない用語かもしれません。
これは、読んで字のごとく、人の「死」亡を原「因」として効力が発生する「贈与」のことです。
通常の贈与だと、あげる人(=贈与者)ともらう人(=受贈者)がどちらも生きている状態で、贈与者から受贈者への財産の移転がおこなわれます。
これに対して、「死因贈与」では、予め、「贈与者が死亡した場合に、●●を受贈者にあげます」と合意しておき、贈与者が亡くなった段階で、受贈者にその指定された財産が移転するということです。
贈与の対象は、金銭や不動産など形のあるものに限らず、配偶者居住権や貸金債権などの権利も「死因贈与」することができます。
「相続」や「遺贈」との違い

人の死亡を原因として財産移転の効力が発生するものには、「死因贈与」以外にも「相続」と「遺贈」があります。
それぞれ「死因贈与」とどのように違うのでしょうか?
「相続」の場合
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の財産が配偶者や子、親や兄弟姉妹などの法定相続人に移転することです。
「死因贈与」との違いは、「死因贈与」は予め贈与者と受贈者との間で合意(契約)しておく必要があるのに対し、「相続」はそのような合意(契約)は何もしておかなくても自動的に財産移転の効果が生じるという点です。
「遺贈」の場合
「遺贈」とは、遺言によっておこなう贈与、すなわち、遺言によって被相続人の財産が他の人に移転することです。
財産をもらう人(受遺者)は、法定相続人のこともあれば、友人・知人など第三者のこともあります。
「死因贈与」との違いは、「死因贈与」は贈与者と受贈者との合意(契約)であるのに対し、「遺贈」は被相続人の一方的な意思表示による単独行為であるという点です。
「死因贈与」のやり方

「死因贈与」は、贈与者と受贈者との間で、予め、「贈与者が死亡した場合に、●●を受贈者にあげます」と合意しておきさえすればよく、書面にしておくことは必須ではありません。
つまり、口頭の合意だけでも「死因贈与」契約は成立するのです。
しかし、皆さんにも容易に想像できると思うのですが、口頭の合意だけで成立するからといって全く書面を残さないというのは考えものです。
贈与者が亡くなった後、受贈者が贈与者の相続人に対して、ある遺産が「死因贈与」の対象になっていたことを主張しようにも、客観的な証拠がないのでは「言った・言わない」の水掛け論になってしまう可能性があります。
そこで、将来のトラブルを未然に防止するためにも、「死因贈与」は書面(契約書)の形でしっかりと残しておくべきでしょう。
「死因贈与」の撤回の可否

【ケース1】
AさんとBさんの間で、「Aは、Aが死亡した時に、Bに対してA所有のマンションを贈与する」との「死因贈与」契約が取り交わされたとします。
数年後、Aさんの気が変わり、「やっぱりBにはマンションをあげたくないな」となった場合、Aさんはこの「死因贈与」契約書を撤回できるでしょうか?
この場合、Aさんは、「死因贈与」契約を撤回することができます。
「死因贈与」契約には「遺贈」の撤回に関する規定が準用されるため、贈与者であるAさんはいつでも「死因贈与」契約を撤回することができるのです。
【ケース2】
AさんとBさんの間で、「Aは、BがAと同居してAの面倒を看ることを条件に、Aが死亡した時に、Bに対してA所有のマンションを贈与する」との「死因贈与」契約書が取り交わされたとします。
しかし、いつまで経ってもBさんはAさんと同居せず、Aさんの面倒も看てくれません。
失望したAさんが、「約束が違うから、Bさんにマンションをあげたくない」と考えた場合、Aさんはこの「死因贈与」契約を撤回できるでしょうか?
この場合、Aさんは「死因贈与」契約を撤回することができます。
今回のケースでは、「死因贈与」契約の中身に、「BがAと同居してAの面倒を看ること」という条件が付いており、このような「死因贈与」契約を「負担付き死因贈与」契約と言います。
「負担付き死因贈与」契約で、受贈者(Bさん)が負担を履行しなかったときは、負担付き遺贈の撤回の規定を準用して、贈与者(Aさん)はこの「負担付き死因贈与」契約を撤回することができるのです。
【ケース3】
AさんとBさんの間で、「Aは、BがAと同居してAの面倒を看ることを条件に、Aが死亡した時に、Bに対してA所有のマンションを贈与する」との「死因贈与」契約書が取り交わされたとします。
Bさんはこの契約に従ってさっそくAさんと同居し、Aさんの身の回りの面倒を看る生活が始まりました。
ところが、数年後、Aさんの気が変わり、「やっぱりこのマンションはBではなく、Cにあげよう」となった場合、Aさんはこの「死因贈与」契約を撤回できるでしょうか?
この場合、Aさんは「死因贈与」契約を撤回することはできません。
今回も「負担付き死因贈与」契約ですが、【ケース2】と異なり、BさんはAさんと同居してその面倒を看始めており、Bさんがすでに負担の一部を履行しています。
このような場合にまで贈与者(Aさん)の気分次第で撤回を許してしまうと、将来マンションをもらえると信じて負担を履行しているBさんにとって酷な結果となってしまいます。
そのため、「負担付き死因贈与」契約で、負担が全部または一部履行されたときは、特段の事情がない限り、贈与者による一方的な撤回は認められないのです。
【ケース4】
AさんとBさんの間で、「Aは、Aが死亡した時に、Bに対してA所有のマンションを贈与する」との「死因贈与」契約書が取り交わされたとします。
10年後、Aさんが亡くなった後で、Bさんの気が変わり、「やっぱりこのマンションは要らないな」となった場合、Bさんはこの「死因贈与」契約を撤回できるでしょうか?
この場合、Bさんは、「死因贈与」契約を撤回することはできません。
「死因贈与」契約において、贈与者が亡くなった後については、原則として、受贈者(Bさん)がこれを撤回することはできません。
「死因贈与」契約が口頭だけでなされたものであった場合は撤回できましたが、本件では契約書が作成されているため、原則どおり撤回できないのです。
「遺贈」と異なり、放棄することもできませんから、Bさんはマンションを取得するほかありません。
撤回の方法について

さて、ここまで4つのケースを見てきましたが、「死因贈与」契約の撤回が認められる場合、その撤回はどのようにすればよいのでしょうか?
この点は、相手方に撤回の意思表示が到達すれば撤回の効力が発生すると考えられていますので、後々のトラブル防止のためにも、内容証明郵便を用いることをお勧めします。
また、撤回の内容証明郵便を送るのではなく、作成した遺言書の中に、「●●年●月●日にBとの間で締結した、マンションを対象とする死因贈与契約を撤回する」と記載しておくのも、撤回の方法として有効です。

父との間で土地をもらう旨の死因贈与契約書を取り交わしていたのに、父の遺言書にはその土地を姉に相続させると書かれていました。
この場合、どちらが優先するのですか?
この場合は、死因贈与契約書と遺言書の作成日付の新しい方が優先されます。
もし、お父様が死因贈与契約書を交わした後に遺言書を作成していた場合は、その遺言書をもって死因贈与契約を撤回したものと評価されるのです。
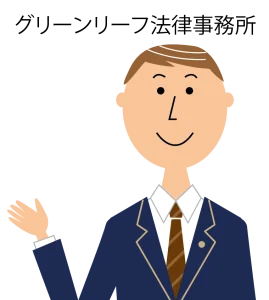

負担付きでない死因贈与だと、そのように撤回できてしまうから、本当にもらえるのかどうか不安ですよね。
死因贈与契約書を取り交わした後、その土地に仮登記をしておけば、撤回を防げますか?
残念ながら、仮登記をしても死因贈与の撤回を防ぐ法的効果はありません。
ただし、撤回を防ぐ事実上の効果はあるかもしれませんよ。
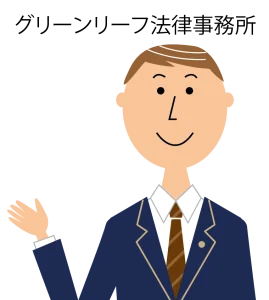

事実上の効果って、どういうことですか?
仮登記をした場合でも撤回自体は自由にできるのですが、一度入れた仮登記を抹消するためには、原則として受贈者の協力が必要です。
お父様から、「あの死因贈与はなかったことにしたいから、仮登記の抹消に協力してくれ」と言われて、すんなりと協力できますか?
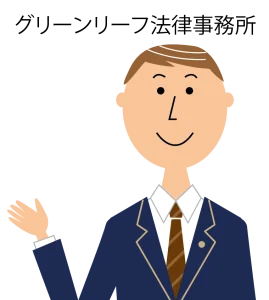

自分の不利になることだし・・・すんなりとは協力できませんよね。
そうですよね。
ですから、仮登記をするにはお父様も慎重になるでしょうし、仮登記までしてもらうということは、以降、簡単には(撤回に伴う)仮登記の抹消ができないという点で、撤回を防ぐ効果が期待できるかもしれないということです。
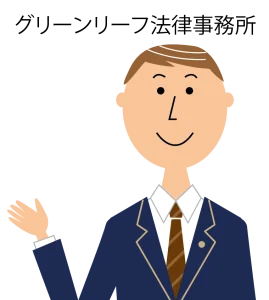
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






