
「遺贈」と「相続」は、どちらも人の死亡を原因として財産が移転するものであり、似たような概念と捉えられがちですが、法律上は明確な違いがあります。本稿ではこれらの違いや、遺贈のメリット・デメリットについて、基礎的な事項を弁護士が解説します。
「遺贈」とは?

「遺贈」とは、遺言によっておこなう贈与、すなわち、遺言によって被相続人の財産が他の人に移転することです。
財産をあげる人のことを「遺贈者」、財産をもらう人のことを「受遺者」と呼びます。
受遺者は法定相続人のこともあれば、友人・知人など第三者のこともあります。
また、特定の個人だけでなく、病院や施設、NPO法人などの法人が受遺者になることも可能です。
贈与の対象は、金銭や不動産など形のあるものに限らず、配偶者居住権や貸金債権などの権利も「遺贈」することができます。
「相続」との違い

「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の財産が配偶者や子、親や兄弟姉妹などの法定相続人に移転することです。
「遺贈」と「相続」の大きな違いは、
■被相続人の行為が必要かどうか
「遺贈」は、被相続人の行為(ある財産を特定の人に贈与する旨の遺言を作成しておく)が必要である
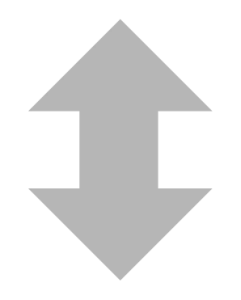
「相続」は、被相続人が特に何もしなくても自動的に財産移転の効果が生じる
■財産をもらう人は誰か
「遺贈」は、法定相続人に限られない
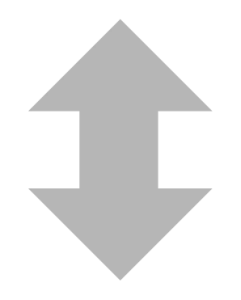
「相続」は、法定相続人に限られる
という点です。
「生前贈与」や「死因贈与」との違い

先に見た定義からも明らかなように、「遺贈」は贈与の一種です。
贈与と言えば他に、「生前贈与」と「死因贈与」があります。
「生前贈与」は、被相続人が亡くなる前に(=まさに「生前」に)財産を贈与することであり、「死因贈与」は、被相続人の死亡を原因として効力が発生する贈与のことです。
いずれも、「遺贈」と同じく、財産をもらう人は法定相続人に限られず、友人・知人などの第三者や法人であっても構いません。
「遺贈」との大きな違いは、
「遺贈」は、被相続人の一方的な意思表示による単独行為である
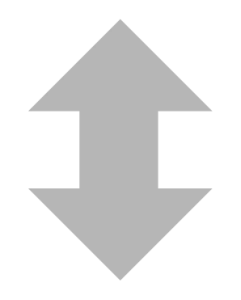
「生前贈与」「死因贈与」は、財産をあげる人(=贈与者)と財産をもらう人(=受贈者との合意(契約)である
という点です。
つまり、「遺贈」の場合は、予め受遺者と合意しておく(受遺者の了解を取っておく)必要がありませんから、受遺者に内緒で、「お世話になったあの人に財産を遺してあげたい」ということが可能なのです。
「包括遺贈」と「特定遺贈」

さて、「遺贈」には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
同じ「遺贈」でも、このどちらであるかによって法的には大きな違いがあり、受遺者自身や相続人に与える影響も異なりますので、詳しく見てみましょう。
「包括遺贈」とは

「包括遺贈」とは、贈与する財産を特定せずに全部の遺産を贈与する場合です。
この他、「遺産全体の4割をあげる」、「遺産全体の2分の1をあげる」というように、割合を指定して贈与する場合も含まれます。
この「包括遺贈」の特徴は、あたかも「相続」のように、被相続人の遺産の一切合切を引き継ぐという点です。
つまり、遺産の全部(または何割か)につき「包括遺贈」を受ける場合、その遺産の中には、プラスの財産(=資産)だけでなく、マイナスの財産(=負債)も含まれている可能性があるのです。
例えば、預貯金や不動産などの資産が5000万円、負債が2000万円あるという被相続人から、遺産の全部につき「包括遺贈」を受けた受遺者は、5000万円の資産だけでなく、2000万円の負債も引き継がなければなりません。
同じ例で、「遺産の2分の1を遺贈する」との遺言により「包括遺贈」を受けた受遺者は、2500万円の資産の他に、1000万円の負債も負わなければならないのです。
「特定遺贈」とは

これに対して、「特定遺贈」とは、贈与する財産を特定して贈与する場合です。
例えば、「さいたま市の土地をA氏にあげる」、「B財団に●●銀行●●支店の預金をあげる」というケースです。
この「特定遺贈」の場合は、贈与される財産が特定されていますので、被相続人から引き継ぐのはその特定の財産だけであり、「包括遺贈」のように、予期せぬ負債がセットでついてくるということはありません。
「遺贈」を拒否したい場合はどうする?

先に、「遺贈」の場合は、予め受遺者と合意しておく(受遺者の了解を取っておく)必要がありませんから、受遺者に内緒で、「お世話になったあの人に財産を遺してあげたい」ということが可能です、とお伝えしました。
これは、裏を返すと、自分の全く知らないうちに、ある人から財産を「遺贈」されているかもしれないということです。
また、受遺者の側から見れば、「財産をもらって嬉しい」という場合ばかりとは限りません。
現金そのものや、比較的換価が容易な株式などであればまだしも、使用する当てもなく、売却も困難な不動産など、いわゆる負の遺産のようなものを託されても、負担ばかりが重くて困ってしまいます。
あたかも「相続」のように、被相続人の遺産の一切合切を引き継ぐことになる「包括遺贈」では、プラスの財産(=資産)よりも、圧倒的にマイナスの財産(=負債)が多いというケースもあり得ます。
このように、受遺者が望まない「遺贈」を拒否する方法はないのでしょうか。
「遺贈」も放棄できる

「相続」において相続人が相続放棄することが認められているように、「遺贈」においても、受遺者は望まない「遺贈」を放棄することができます。
「包括遺贈」と「特定遺贈」とで、放棄の方法が異なりますので、順次説明します。
「包括遺贈」を放棄する方法
「包括遺贈」は、あたかも「相続」のように、被相続人の遺産の一切合切を引き継ぐことになりますので、放棄の方法も相続放棄と同じになります。
すなわち、自分に対して「包括遺贈」があった事実を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「遺贈」を放棄する旨の申述を行います。
“自分に対して「包括遺贈」があった事実を知った時”とは、例えば、ある人が残した遺言に、「全ての遺産を●●(=自分)に遺贈する」との記載があることを知った時などです。
申述の書類を提出する先は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続きは郵送でも可能です。
仮に、3か月が過ぎても「遺贈」を放棄する旨の申述をしなかった場合には、その「包括遺贈」を受けることを承認したとみなされますので、受遺者は、以後「遺贈」の放棄ができなくなります。
「特定遺贈」を放棄する方法
「特定遺贈」を放棄する場合は、相続人や遺言執行者に対してその「遺贈」を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
具体的には、「●●(=遺贈された財産)についての遺贈を放棄します」という内容証明郵便を、相続人や遺言執行者に郵送します。
「特定遺贈」を放棄する場合は、「包括遺贈」と異なり、いつまでにしなければならないという期間制限はありません。
しかし、受遺者がその「特定遺贈」を受けるのかどうか、何年も態度をはっきりさせないままでは、相続人はいつまでも遺産の分割ができないことになり、大変な迷惑を被ります。
そのため、相続人などの利害関係者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に「特定遺贈」を承認するか放棄するかを決めるよう、催告することができます。
催告期間内に回答をしなかった場合、受遺者はその「特定遺贈」を承認したものとみなされ、以後、放棄することはできなくなります。
「遺贈」のメリットとデメリット

これまで見てきたように、「遺贈」は、被相続人の死亡を原因として財産が移転する点で「相続」と同じであり、また、贈与の一種であるという点では「生前贈与」や「死因贈与」と一緒です。
それでは、「相続」させるのでもなく、「生前贈与」や「死因贈与」をするのでもなく、あえて「遺贈」という方法を取ることにメリットはあるのでしょうか。
「遺贈」のメリット

①法定相続人以外の人にも財産を残せる
「相続」の場合、配偶者や子、親や兄弟姉妹などの法定相続人にしか自分の財産を残すことができません。
しかし、「遺贈」であれば、法定相続人ではない親族や、全く親族関係のない第三者(友人、知人)にも財産を残すことができます。
つまり、法律の決めた枠にとらわれることなく、自分が本当に財産を譲りたい相手を指定して、財産を残すことができるのです。
②法人にも財産を残せる
「相続」の場合、財産を引き継ぐことができるのは相続人という個人(自然人)であって、会社などの法人に財産を引き継がせることはできません。
しかし、「遺贈」であれば、個人だけでなく、会社や財団などの法人に対しても財産を引き継がせることができます。
このため、その活動に賛同する公私の団体を指定して、今後の応援の気持ちを込めて自分の財産を託す、ということが可能なのです。
③財産を受け取る人に内密で進めることができる
「生前贈与」や「死因贈与」では、被相続人が亡くなる前に、被相続人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者として、贈与契約を取り交わしておく必要があります。
つまり、当事者双方の合意が必要となりますから、受贈者に秘密にしたまま事を進めるということはできません。
しかし、「遺贈」であれば、遺言者の一方的な意思表示で足りますから、受遺者と事前に合意しておく必要はなく、受遺者に秘密にしたまま事を進めることができます。
「生前にお世話になったあの人へサプライズで財産を残す」ということが可能なのです。
「遺贈」のデメリット

「遺贈」には以上のようなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
①望まぬ「遺贈」は放棄される可能性がある
これは、メリット③の裏返しとも言えるのですが、「遺贈」は遺言者の一方的な意思表示によって行われるため、受遺者がその「遺贈」を有り難く受け取ってくれるかどうかわからないという面があります。
その「遺贈」が、受遺者の望まないものであった場合、先に見たように、受遺者は「遺贈」を放棄するかもしれません。
特に、「遺贈」する先が法人である場合には、現物の不動産では受け入れる体制がなく、現預金のみしか受け取ってもらえないということもあるでしょう。
せっかく良かれと思って「遺贈」したのに、希望とのミスマッチが原因で放棄されてしまったのでは、遺言者としても非常に残念ですよね。
このような事態を避けるためには、たとえ「遺贈」の形を取るにしても、事前に受遺者の承諾を取っておくことが望ましいと言えます。
②遺留分侵害額請求に巻き込まれるリスクがある
「遺贈」、特に「包括遺贈」の場合には、被相続人の全ての財産が受遺者の方にいってしまい、法定相続人は何も取得することができません。
このため、受遺者は、最低限の取り分さえ取得できなかった相続人から、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分侵害額請求を受けた受遺者は、原則として、金銭の形で侵害額を支払わなければなりません。
引き継いだ遺産の中に十分な流動資産があればよいですが、遺産の大部分がすぐには換価することの難しい不動産で占められている場合は、受遺者が自分の財産の中から相続人に支払う金額を工面しなければならない―――という事態もあり得るのです。
こうなっては、遺言者が感謝の気持ちを示そうと思っておこなった「遺贈」が、かえって受遺者を相続トラブルに巻き込むこととなり、善意でした行為が裏目に出てしまいます。
このような事態を避けるため、法定相続人が存在する場合は「包括遺贈」を避け、なるべく「特定遺贈」の形を取るべきでしょう。
ただし、「特定遺贈」の場合であっても、法定相続人に、最低限遺留分に相当するだけの財産は行き渡るよう、配慮する必要があります。
「遺贈」するかどうかで迷ったら専門家に相談を

これまで見てきたとおり、「遺贈」は「相続」とは似て非なるものであり、同じ贈与である「生前贈与」や「死因贈与」とも異なる点があります。
また、どのような制度でもそうですが、「遺贈」にもメリットがあれば、その反面としてのデメリットもあるのです。
「遺贈」に関する正しい法的知識に基づき、そのメリットとデメリットを比較衡量したうえで、それでもなお「遺贈」を選択するのか(選択すべきなのか)。
判断に迷われた場合は、是非、専門家である弁護士に相談して下さい。
良かれと思ってした「遺贈」がかえって受遺者の負担となり、受けた恩を仇で返すような結果となってしまっては元も子もありません。
それぞれのケースで最適な選択はどれなのか、一緒に検討していきましょう。






