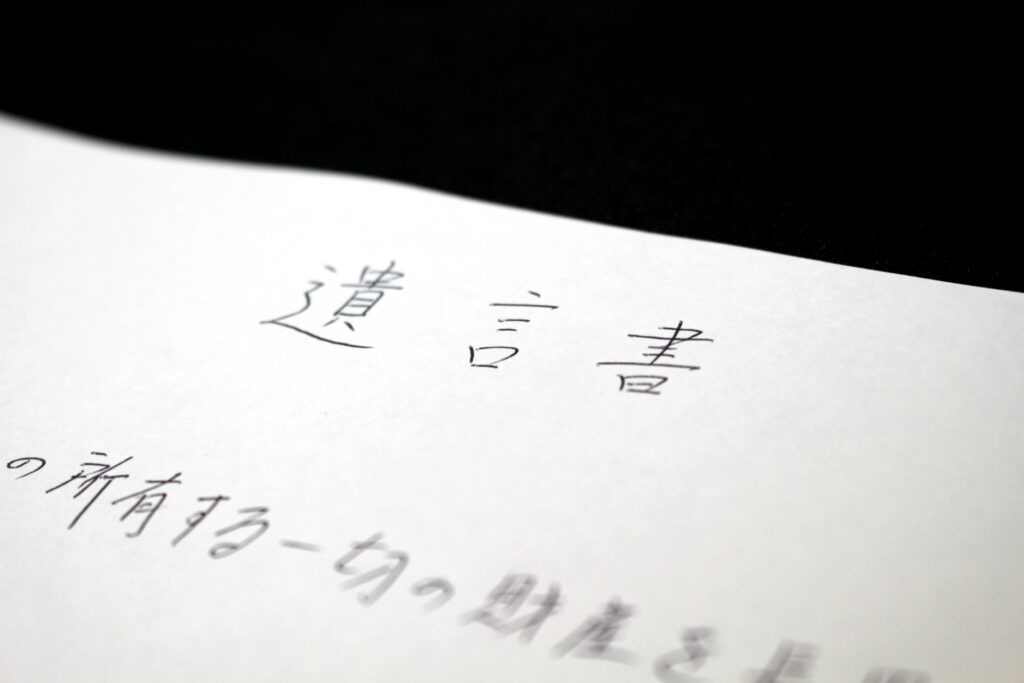
相続人が遺言者より先に亡くなった場合に備えて次に相続する人を指定しておくのが、「予備的遺言」です。「予備的遺言」をしておかないと、遺言者の希望とは別の形で財産が流れて行ってしまう可能性もあります。作成の際の注意点と併せて弁護士が解説します。
「予備的遺言」ってどのようなもの?

“終活”という言葉がブームになって久しい昨今、その一環として遺言書(法律上の用語では「遺言」といいます)の作成を考えている方も増えていると思います。
この遺言に関連して、「予備的遺言」という用語を聞いたことはあるでしょうか。
「本物の遺言書がなくなってしまった場合に備えて作っておく、予備の遺言書のことかな?」とも思いがちですが、そうではありません。
「予備的遺言」とは、相続人(遺言書で遺産を取得させることにしたその人)が遺言者(遺言書を書いた人)より先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておく遺言のことです。
「予備的遺言」をしておかないとどうなるか

例えば、次のようなケースで考えてみましょう。
Aさんには、長男B、長女Cの2人の子供がいます。
長男Bにはこれまで十分に金銭的援助をしてきたので、残りの遺産は全て長女Cに取得させたいと考えたAさんは、
「全ての財産を長女Cに相続させる」
という遺言を作成しました。
ところが、遺言書作成後、不幸にも、Aさんは長女Cと旅行中に交通事故に遭い、二人ともその事故で亡くなってしまいました。
このような場合、Aさんが生前に作成していた「全ての財産を長女Cに相続させる」という遺言はどうなってしまうと思いますか?
まず、同じ事故で亡くなったAさんと長女Cは、同時死亡の推定(民法32条の2)により、法的には全く同時に亡くなったものと推定されます。
これは何を意味するかというと、Aさんと長女Cとの間では、相互に相続が開始しない(民法882条)ということです。
その結果、Aさんが生前に作成していた「全ての財産を長女Cに相続させる」という遺言は意味をなさない(無効である)ことになってしまうのです。
そうすると、Aさんの遺産は、結局、残った相続人である長男Cが全て取得することになります。
このような結果を、故人となったAさんは望んでいなかったはずです。
「予備的遺言」で万が一の場合に備える

それでは、Aさんはどのようにしておけばよかったのでしょうか。
ここで、登場するのが「予備的遺言」です。
今度のケースでは、長女Cには子Dがいるとします。
そして、Aさんは、長女Cが自分より先に亡くなってしまった場合、長男Bに遺産が行くよりは、孫のDに取らせてあげたいと考えたとします。
そこで、Aさんは、次のような「予備的遺言」を書きました。
「全ての財産を長女Cに相続させる。ただし、長女Cが遺言者よりも前にまたは遺言者と同時に死亡した場合は、全ての財産を孫Dに相続させる」
上記の「ただし」以下の部分が「予備的遺言」です。
これにより、Aさんと長女Cが交通事故に遭って一緒に亡くなったとしても、また、長女CがAさんより先に亡くなったとしても、遺言書は無駄にならず、Aさんの遺産は全て孫Dが相続することができるのです。
「予備的遺言」が必要なケース

このように、相続人(遺言書で遺産を取得させることにしたその人)が遺言者(遺言書を書いた人)より先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておくのが、「予備的遺言」です。
こうした「予備的遺言」をしておく必要があるのは、一般的には次のようなケースです。
①相続(または遺贈)させる相手の健康状態が優れないケース

遺言書で財産を相続(または遺贈)させることにした相手の健康状態が優れない場合(例えば、末期がんで入院中であるなど)、もしかすると、遺言者(自分)よりその相手の方が先に亡くなってしまうかもしれません。
このような場合は、その相手が死亡してしまった場合に備えて、次に財産を残したい人を指定する「予備的遺言」をしておく必要があると言えるでしょう。
②遺言者と相続(または遺贈)させる相手の年齢が近い場合

遺言書で財産を相続(または遺贈)させることにした相手が、遺言者(自分)と年齢が近い場合、どちらが先に亡くなるか分かりません。
年の近い配偶者や兄弟姉妹などに「全ての財産を相続させる」とだけ書いて、「予備的遺言」をしておかないのでは、自分が意図したのとは違う形で財産が流れていってしまう可能性もありますから、きちんと対策をとりましょう。
「予備的遺言」を作成する場合の注意点

「予備的遺言」と作成する場合には1点、気を付けていただきたいことがあります。
それは、他の相続人の遺留分を害しないようにするということです。
遺留分とは、遺言でも奪うことのできない、相続人の最低限の取り分のことです。
例えば、先の、「全ての財産を長女Cに相続させる。ただし、長女Cが遺言者よりも前にまたは遺言者と同時に死亡した場合は、全ての財産を孫Dに相続させる」という「予備的遺言」を作成したAさんのケースを見てみましょう。
この遺言により、長女Cに万が一のことがあっても、Aさんの遺産は全て孫Dが相続できることになっていました。
ところが、ここで忘れてはならないのが、もう一人の相続人である長男Bの存在です。
長男Bには、遺言でも奪うことのできない遺留分(このケースでは4分の1)があります。
このため、長男Bは、Aさんの遺言によって全ての財産を相続した孫Dに対し、遺留分侵害額請求をすることができます。つまり、遺留分に相当する金額を自分に支払え、と言えるわけです。
これだと、請求を受ける側の孫Dにとっても負担が大きいでしょう。
そこで、このような事態を避けるためには、Aさんが、長男Bの遺留分に配慮した内容の遺言を作成しておくこと、具体的には、財産の全てを長女C・孫Dに相続させるのではなく、遺留分相当額は長男Bも取得できるような内容にしておくことです。
「予備的遺言」の手数料について

遺言書を公正証書の形で作成するには、公証役場に手数料を納める必要があります。
手数料の額は、対象となる財産の価格によって決まります。
ところで、「予備的遺言」を含んだ遺言書を作成する場合と、「予備的遺言」を含まない遺言書を作成する場合で、公証役場に納める手数料の額に違いは生じるのでしょうか。
この点、日本公証人連合会では、公正証書遺言において、主位的な遺言と予備的な遺言とを1通の遺言公正証書に併せて記載する場合には、主位的な遺言によって手数料を算定し、予備的な遺言については手数料の算定しないことになっています。
つまり、「予備的遺言」を含んだ遺言書を作成する場合も、遺言の対象となる財産の価額に対応する手数料の額が増えることはない、ということです。
ただし、「予備的遺言」を1通の遺言公正証書に併せて記載しなかった場合、例えば、まず、主位的な遺言のみの遺言公正証書を作成し、後から、予備的な遺言を追加するために、予備的な遺言の遺言公正証書を作成する場合には、別途、予備的な遺言について手数料がかかるので、注意が必要です。






