
交通事故の後遺障害申請で困っていませんか?
「事故後、首の痛みが引かない…」「手足のしびれで仕事ができない…」
突然の交通事故により、つらい後遺症に悩まされていませんか?
後遺障害の申請は、今後の生活を左右する重要な手続きです。しかし、申請の手続きは複雑であり、適切な等級が認定されなければ、十分な補償を受けることができません。
「本当に適切な等級が認定されるのだろうか…」「保険会社との交渉が不安…」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、後遺障害の申請の前提となる、後遺障害診断書の書き方や、医師へのもらい方について解説します。
後遺障害とは?

後遺障害の定義
後遺障害とは、交通事故による負傷が治療を尽くした後も完治せず、将来的に回復の見込みがない障害を指します。医学的に「症状固定」と判断された段階で、後遺障害の等級認定申請を行うことができます。
後遺障害等級とは?
後遺障害には1級から14級までの等級があり、等級ごとに慰謝料や逸失利益の額が異なります。
| 等級 | 代表的な症状 | 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 1級 | 四肢麻痺 | 2,800万円~3,200万円 |
| 7級 | 手足の一部欠損 | 1,000万円~1,200万円 |
| 14級 | むちうち症状 | 110万円~130万円 |
※上記の慰謝料相場はあくまで目安であり、個別の事情によって変動します。
逸失利益とは?
後遺障害がなければ将来得られたはずの収入の減少分を指します。例えば、事故前は年収500万円だった方が、後遺障害により労働能力を50%喪失した場合、年間の逸失利益は250万円となります。(あくまで一例です。計算方法は複雑です。)
後遺障害の種類としては、自賠責保険で定められたものがあり、例えば、むちうち、関節が動かない、高次脳機能障害、脊髄損傷で麻痺などがあります。
これらは、等級によって受けられる補償が大きく異なるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。
よくある誤解
- 症状が軽いと申請できない? → 軽い症状でも日常生活に支障があれば申請可能です。
- 医師任せで大丈夫? → 医師が適切な診断書を作成してくれるとは限りません。自ら申請のポイントを理解することが重要です。
後遺障害診断書とはなにか
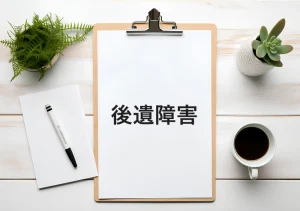
交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害」の申請を検討することになります。その際に必要となるのが「後遺障害診断書」です。しかし、この診断書がどのようなものなのか、具体的に何が書かれているのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
後遺障害診断書とは、交通事故による後遺障害の存在と程度を医学的に証明するための書類です。
医師が作成し、自賠責保険会社や裁判所などに提出します。
この診断書は、後遺障害の等級認定や、損害賠償額の算定において、非常に重要な役割を果たします。
なぜ重要なのか?
- 後遺障害の等級認定の判断材料となる
- 損害賠償額(慰謝料や逸失利益)を算定する際の根拠となる
- 保険会社との示談交渉や裁判で、客観的な証拠となる
後遺障害診断書と通常の診断書の違い

通常の診断書は、病名や治療経過などを記載するものですが、後遺障害診断書は、それに加えて、以下の点が異なります。
- 後遺障害の症状が「症状固定」(これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態)であることを明記する
- 後遺障害の具体的な症状、程度、将来の見通しなどを詳細に記載する
- 後遺障害の等級認定に必要な情報(検査結果、関節可動域など)を記載する
- 他覚的所見を書く欄がある
- 自覚症状を書く欄がある
後遺障害診断書の記載内容
後遺障害診断書には、主に以下の内容が記載されます。
- 傷病名: 交通事故によって負ったケガの名称
- 症状固定日: これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した日
- 自覚症状: 患者が訴える痛み、しびれ、麻痺、めまいなどの症状
- 他覚症状: 医師が診察や検査によって確認した客観的な症状(関節可動域制限、筋力低下など)
- 検査結果: レントゲン、MRI、CT、神経学的検査などの結果
- 後遺障害の内容: 具体的な症状、程度、日常生活への影響など
- 将来の見通し: 今後の症状の経過や回復の見込み
- その他: 既往症、事故との因果関係、労働能力への影響など
これらの項目が詳細かつ正確に記載されているほど、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
すべての医師が、これを理解しているわけではありませんので、医師に任せにすると、認定に不利なものができあげることもあり得ます。
後遺障害診断書を作成する際の注意点

誰が作成するのか?
後遺障害診断書は、医師のみが作成できます。原則として、症状固定の診断を行った医師(主治医)に作成を依頼します。
いつ作成するのか?
症状固定の診断を受けた後に作成を依頼します。症状固定の時期は、ケガの種類や程度によって異なりますが、例えば、むちうちだと、一般的には長くても事故後6ヶ月程度が目安となります。
早すぎる症状固定は、まだ症状が改善する可能性があると判断され、後遺障害として認められないことがあります。
逆に遅すぎる症状固定は、本来受け取れるはずの補償が受けられなくなる可能性があります。
どうやって作成するの?
以下のページから、後遺障害診断書をダウンロードします。
A3で印刷して、病院にもっていきます。病院にデータがあることもあり、紙は不要なケースもあります。
医師に、「症状固定して、後遺障害の申請をしたいので、後遺障害診断書を作成お願いします」と言えば、たいていは問題ありません。
診断書の作成費用は?

後遺障害診断書の作成費用は、医療機関によって異なりますが、5,000円~20,000円程度が一般的です。
自賠責保険や相手保険会社請求できる場合もありますが、一次的には被害者が立替えることが多いです。
医師への依頼のポイント
- 症状を具体的に、正確に伝える(いつから、どのような症状が、どの程度続いているか)
- 日常生活への支障を具体的に伝える(仕事、家事、趣味など、何ができなくなったか)
- 必要な検査(MRI、CTなど)を受けているか確認する
- 診断書の内容をよく確認し、不明な点や疑問点は医師に質問する
後遺障害診断書は、交通事故による後遺障害の存在と程度を証明する重要な書類です。適切な後遺障害等級の認定を受け、適正な補償を受けるためには、この診断書の内容が非常に重要になります。
まずは医師にしっかりと症状を伝えましょう。特に自覚症状は伝えないと医師がカルテを参考に適当に書くこともあります。
医師が書いてくれないときは?
経験上、最後まで書いてくれないという医師はいませんが、最初に断わる医師は、理由があるときも多いです。
1.後遺障害は残っていないと言われた
医師は、保険上や賠償上の後遺障害のことをよくわかっていない事もあります。そういう場合は、「ここで後遺障害と判断するのではなく、あくまで自賠責保険で審査するので、ありのままの症状とデータを記載してください」などと依頼するとうまくいったケースがあります。
2.全然看ていないのでわからないと言われた
大きな病院では、担当医師が変わる場合もあります。そのときは、「カルテどおり書いてください」と言ってみましょう。
どのような理由でも、「保険の申請で必要なのです。お願いします」と言えば、最終的には協力してくれると思います。
後遺障害申請の落とし穴

① 不適切な診断書
後遺障害の認定は診断書の内容に大きく左右されます。症状が十分に記載されていない、必要な検査結果(MRI、CT、神経学的検査など)が記載されていないと、適切な等級が認められない可能性があります。
② 症状固定の時期の誤り
症状固定が早すぎると、まだ症状の改善が見込めると判断され、不利になる可能性があります。一方で遅すぎると、適切な時期に申請ができず、補償を受けられないこともあります。
③ 申請書類の不備
申請書の記入ミスや、必要書類の不足は、自賠責の認定が遅れる原因になります。漏れなく正確な情報を提出することが重要です。
これらは、被害者個人でチェックするのは難しいかもしれません。
グリーンリーフ法律事務所では、後遺障害診断書の書く前のチェックや、書いた後のチェックも行っています。
【ケーススタディ】
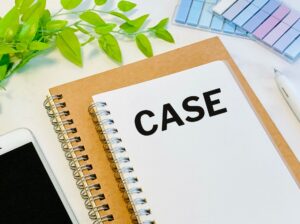
ケース1:診断書の不備で等級が低くなった事例
- 事故によるむちうちで14級を申請 → 診断書に具体的な症状の記載や検査結果が不足 → 非該当
- 弁護士介入 → 必要な検査を実施し、詳細な診断書を再提出 → 12級認定を獲得、賠償額が200万円増額
ケース2: 症状固定の時期が早すぎた事例
- 事故後3ヶ月で症状固定と診断され、後遺障害申請 → 非該当
- 弁護士介入 → 適切な治療継続と経過観察をアドバイス →健康保険で治療再開し、 事故後6ヶ月で再度症状固定と判断、14級認定を獲得
ケース3:保険会社との交渉で不利になった事例
- 後遺障害14級相当の症状 → 保険会社は「後遺障害には該当しない」と主張
- 弁護士介入 → 医学的証拠に基づき交渉 → 示談金が当初提示額の3倍に
等級認定を勝ち取るためのポイント

① 適切な医療機関の選択
交通事故診療に詳しい医師、後遺障害診断書の作成に慣れている医師を選ぶことで、適切な診断書を作成してもらいやすくなります。
いくつか病院に通っている場合は、主治医が本来は望ましいが、場合によってはセカンドオピニオンも選択肢に入ります。
② 医師とのコミュニケーション
診察時に以下の点を明確に伝えましょう。
- 事故の状況(いつ、どこで、どのように)
- 事故直後からの症状の変化(具体的に、時系列で)
- 現在の症状(痛み、しびれ、可動域制限など、具体的に)
- 日常生活への支障(仕事、家事、趣味など、具体的に)
症状の変化を伝える際は、「事故直後は首が全く動かなかったが、今は少し動くようになった。しかし、30分以上同じ姿勢でいると痛みが増す」のように具体的に表現しましょう。
医師に「必要な検査をお願いします」とはっきり伝えることも重要です。
例えば、レントゲンしか撮らない医師もいますし、MRIまで指示する医師もいます。痛みが酷い場合は、念のためMRIまで撮ることが望ましいケースもあります。
③ 症状の記録
可能であれば、事故直後からの症状の変化や日常生活への支障を、日記や写真、動画などで記録しておきましょう。
痛みの程度を10段階で評価したり、日常生活での具体的な支障(「階段の上り下りがつらい」「ペットボトルが開けられない」など)を記録することが有効です。記録には、日記アプリ、写真アプリ、ボイスレコーダーなどが活用できます。
ここまでやっている方はなかなかいませんが、訴訟等で証拠にできることもあります。
④ 必要な検査の受診
上と被りますが、MRI、CT、神経学的検査など、症状に応じた検査を受けることで、後遺障害が医学的に証明されやすくなります。
⑤ 申請書類の準備
申請書類は細部までチェックし、必要な資料をすべて添付することが大切です。
不備があると、再提出を求められ、認定が遅れる原因になります。
また、実は、自賠責で必要とされている書類以外にも、自由に書類を提出することはできます。
例えば、物損の資料、日記、写真、陳述書などです。これらは、審査に有用と思えるものは添付するべきです。
⑥ 異議申し立て
認定結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行うことで再審査を受けることができます。必要書類は、異議申立書、新たな医学的証拠などです。
交通事故を弁護士に相談するメリット

後遺障害申請は複雑で難しく、一人で対応するのは困難です。しかし、適切な準備と弁護士のサポートがあれば、適正な等級認定を受け、十分な補償を得ることができる可能性が高まります。もちろん難しいケースもありますが、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
また、交通事故は、相手の保険会社と争いになることが多く、また、気づかないまま、相場より低い水準で合意(示談)してしまうケースが多いです。
もし、後遺障害が残ると保険金額(逸失利益や慰謝料)が大きくなるので、被害者が損をする金額が大きくなる可能性があり、保険会社と争いになる確率も多くなります。
実際、弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所が委任を受けた事件でもそのような事案があります)。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、ご自身の保険で、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険でまかなえます。
※ご自身が、弁護士特約に加入しているかどうかは、保険証券をみるか、加入している保険会社にお問い合わせください。
弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、小さな事でもまずは、法律相談していただくことをおすすめします。
当事務所では、ライン(LINE)での相談も行っています。
友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
弁護士特約について詳しくは、こちらをご覧ください。
ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
もし交通事故でお悩みの方や、交通事故被害者のご家族の方がこの記事をご覧の場合、当事務所では、適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。






