
交通事故に遭った際、頭部を強く打つことは珍しくありません。一見軽症に見えても、時間が経つにつれて重篤な症状が現れることもあります。一時的にまたは場合によっては永続的に意識不明状態になってしまうことがあります。特に、自転車や徒歩の状態で衝突されると、頭部がむきだしなので意識不明の重体になる確率が高まります。本記事では、埼玉で交通事故に強い弁護士事務所が、交通事故による頭部外傷のリスク、症状の種類、適切な対処法について詳しく解説します。
頭を打った直後に現れる主な症状

交通事故などで頭を強く打った場合、脳に損傷が起きている可能性があります。以下のような症状が現れることがあり、軽度に見えても、時間の経過とともに症状が悪化する場合があるため、注意が必要です。
軽度な症状
- 軽い頭痛: ズキズキ、ガンガンといった拍動性の頭痛や、締め付けられるような頭痛など。
- めまい: ふわふわする、回転するような感覚。
- 吐き気・嘔吐: 吐き気を催したり、実際に嘔吐したりする。
- 一時的な意識の混濁/記憶障害: ぼんやりする、事故前後の記憶がない、同じことを何度も聞く。
- 耳鳴り: キーンという音が聞こえる。
- 目のかすみ: 視界がぼやける、二重に見える。
- 倦怠感: 体がだるい、疲れやすい。
重度な症状
- 強い頭痛が続く: 時間経過とともに悪化する、または強い痛みが続く。
- 意識障害: 意識がもうろうとする、呼びかけに反応しない、反応が鈍い、昏睡状態。
- 言語障害: 話しづらい、言葉が出てこない、ろれつが回らない。
- 手足のしびれや麻痺: 片方の手足、または両方の手足がしびれる、力が入らない。
- 痙攣発作: 体の一部または全身がけいれんする。
- 瞳孔不同: 左右の瞳孔の大きさが異なる。
上記のうち、特に重度な症状が見られる場合は、すぐに救急車を呼び、医療機関を受診する必要があります。一見重度でなくても、後から症状がでることはあり得るので、頭を打った場合は、すぐに病院に行く必要があると考えます。
頭の場合は、脳神経外科になります。MRIやCT、レントゲンで脳内の検査をうけてください。
後で解説する高次脳機能障害が発生した場合の重要証拠にもなります。
数日後に遅れて現れる症状と注意点

交通事故による頭部外傷の影響は、事故直後だけでなく、数日後に現れることがあります。
遅れて現れる可能性のある症状
- 持続的または悪化する頭痛
- 吐き気や嘔吐が続く
- 集中力の低下や記憶障害
- 手足のしびれや運動障害
- 意識が遠のく感じや極端な眠気
特に、「硬膜下血腫」や「くも膜下出血」などの深刻な合併症は、事故から数時間~数日後に症状が現れることがあります。事故後は自己判断せず、病院で検査をして、医師の指示に
従うようにしてください。
頭部を打つにより起こりうる病状
・軽度の頭部外傷(軽度外傷性脳損傷 / 脳震盪)
・中等度の頭部外傷(脳挫傷・びまん性軸索損傷)
※びまん性軸索損傷(DAI: Diffuse Axonal Injury)では、脳内の神経線維(軸索)が広範囲に損傷され、意識障害が長期化する可能性がある。 受傷直後は軽症に見えても、時間の経過とともに症状が悪化する場合があるため、慎重な経過観察が必要。
・重度の頭部外傷(硬膜外血腫・硬膜下血腫・くも膜下出血)
→脳を包む血管が破れ、脳内や頭蓋内に血液が貯留し、脳圧の上昇や脳組織の圧迫が発生する。
・急性硬膜下血腫(ASDH: Acute Subdural Hematoma)
・慢性硬膜下血腫(CSDH: Chronic Subdural Hematoma)
・頭蓋骨骨折
- 線状骨折(比較的軽度だが、脳挫傷を伴うことがある)
- 陥没骨折(脳を圧迫し、手術が必要になる場合がある)
- 頭蓋底骨折(脳脊髄液の漏出、顔面神経麻痺を伴うことがある)
事故直後に被害者がすべき適切な対処法

1. すぐに医療機関を受診する
交通事故で頭を打った場合、症状が軽くても病院でCTやMRI検査を受けることが重要です。
2. 安静を保つ
事故直後はできるだけ動かず、頭を強く揺らさないようにしましょう。また、睡眠中に意識障害が進行する可能性があるため、事故後数時間は誰かが付き添うことが望ましいです。
3. 再受診の重要性
事故後しばらく経ってから症状が悪化した場合は、すぐに病院を受診してください。特に、頭痛が強まる、吐き気が続く、意識がもうろうとするなどの症状がある場合は要注意です。
医療機関受診後の対応・手続きについて

1. 診断書の取得
病院での診察後、診断書を発行してもらいましょう。診断書は保険請求や損害賠償請求の際に必要になります。
2. 保険会社への報告
事故の状況や受診した医療機関の情報を自社の保険会社と相手の保険会社(分かり次第)に伝え、手続きを進めます。
3. 後遺障害認定や損害賠償請求のための弁護士相談
事故の影響で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。適切な損害賠償を受けるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故による損害の種類と賠償請求

頭部外傷で発生する可能性のある損害
交通事故で頭部を負傷した場合、以下のような損害が発生する可能性があります。
(1)治療費
- 診察費、検査費(CT・MRI等)、処方薬の費用
- 手術費、リハビリ費、入院費
- 通院時の交通費や付き添いの介護費用
(2)休業損害
- 会社員:給与の減額分、ボーナス減額分
- 自営業者:売上減少分、営業活動の停止による損失
- パート・アルバイト:シフトキャンセルによる収入減少
(3)慰謝料
- 入院・通院に伴う精神的苦痛の補償(自賠責基準・弁護士基準による算定)
(4)後遺障害による逸失利益
- 労働能力喪失率に基づく将来の収入減少の補償
- 事故前の職業や収入水準を考慮した逸失利益の算出
- 主婦・学生の場合の家事労働や将来の収入補償
交通事故被害者が意識不明の場合は誰が加害者(保険会社)と交渉すれば良いか
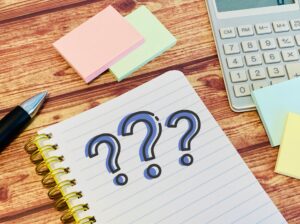
当然、意識不明の方は、自ら加害者や保険会社に対して保険金の請求をすることができません。大体の場合は、まずは、被害者の代わりにご家族が保険会社と交渉することになります。
ただし、ご家族が、「示談」をすることができるかというと、そのままでは示談ができません。なぜなら、意識不明といえども、個人の権利(損害賠償の権利)を、家族が勝手に使うことはできないからです。
その場合は、成年後見制度を使うことになります。
交通事故と成年後見

■「交通事故で遷延性意識障害となり、意識がもどらない」
■「保険会社から示談をするためには成年後見人をつける必要があると言われた」
保険会社と示談をするためには、一定の判断能力が必要となります。しかし、ご本人の意識がないため(あっても意思を表明できない)、いつまでも示談ができない事になってしまいます。弁護士を代理人にしようとしても、本人が弁護士とも契約ができない状態です。
なお、被害者が未成年の方であれば,ご両親が法定代理人として示談を行うことができます。
問題は、被害者が成年者の場合です。この場合、ご両親が被害者を代理して示談交渉を行うことはできません。
このような場合には、『成年後見』という制度を活用することができます。
当事務所では成年後見手続きのお手伝いもしております。
■成年後見制度とは
本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、家庭裁判所が本人の代理人(後見人)を選び、本人の財産等を法律的に保護しようという手続きです。
したがって、示談交渉や裁判をするためには、まず、家庭裁判所から「成年後見人」を選任してもらった上で、成年後見人に示談交渉や裁判(ほかに、弁護士への依頼等)をしてもらう必要があります。
成年後見の申立には、各種申立書類(申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録及びその疎明資料、本人の収支報告書及びその疎明資料、後見人等候補者事情説明書、戸籍謄本、住民票等)が必要となります。
また、申立て後には、裁判所での面接も実施されることがほとんどです。
このように、様々な書類を用意したり、裁判所に提出する文書を作成しなければなりません。ご本人やご家族の負担は大きいと思います。
当事務所では、書類の取り付けや面接への同行等、成年後見申立について、全面的にお手伝いを致します。
■成年後見人に選ばれるのは誰か?
最終的には家庭裁判所が決めることになりますが、申立て時には、候補者を届け出ることができます。通常は、ご本人に近いご親族が多いかと思います。
また、成年後見人に選ばれると、財産報告や定期報告等の義務が生じるので、ある程度は負担になってしまいます。そのようなときは、当事務所弁護士が、成年後見人の候補者となることもできます。
ご親族同士に争いがある場合は、第三者である弁護士を候補者とするか、裁判所に別の弁護士を選んでもらうことになります。
被害者が未成年の場合を除き、家族が代理で保険会社と交渉するためには「代理権」を授与する「成年後見人」を家族の誰かに選任する必要があります。
★参考ページ
https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/kouken/index.html
意識不明と高次脳機能障害について

交通事故に遭い、頭を強く打った場合、後遺障害として、「高次脳機能障害」と呼ばれる様々な障害が残ることがあります。
最近では、高次脳機能障害という言葉も広く浸透してきて、インターネットで探せば情報がたくさんでてきます。
高次脳機能障害とはどのような症状かというと、以下のような症状が重なっておきることを指します。
①記憶障害
- 物の置き場所を忘れる。・新しいできごとを覚えられない。
- 同じことを繰り返し質問する。
②注意障害
- ぼんやりしていて、ミスが多い。
- ふたつのことを同時に行うと混乱する。
- 作業を長く続けられない。
③遂行機能障害
- 自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
- 人に指示してもらわないと何もできない。
- 約束の時間に間に合わない。
④社会的行動障害
- 興奮する、暴力を振るう。
- 思い通りにならないと、大声を出す。
- 自己中心的になる。
この症状により、日常生活または社会生活に制約がでてくる状態が「高次脳機能障害」と言われる後遺障害です。
意識不明と後遺障害等級との関係について
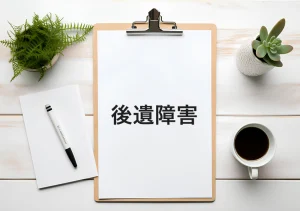
交通事故に遭って、高次脳機能障害が残った場合は、後遺障害の何級に該当するでしょうか。
自賠責保険が認定する後遺障害は、1級から14級まであります。高次脳機能障害は、症状の重さによって、このうちのいくつの級にわかれています。
どういった症状が、どれくらい重いかは、医学的なテストなどで判断します。その結果を参照して、自賠責で等級を判断することになります。
(事故の大きさや、初期症状等も重要です)
| 等級 | 後遺障害認定基準 | 症状 |
| 1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
| 2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの |
| 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの | |
| 5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
| 7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
| 9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
ついた等級により、保険金(賠償額)が大きく変わります。
どれほど変わるかは、こちらのページをご参照ください。
適正な等級を取得するには、やはり専門家にご相談いただくのが良いと思います。
交通事故、とくに後遺障害の分野は、どの弁護士もできるわけではありません。
医者の場合は、整形外科、眼科、消化器内科、耳鼻科などわかれているように、弁護士にも得意分野があります。特に、交通事故は医学的な知識も必要なため、経験の浅い弁護士にでは対処できません。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、「交通事故専門チーム」をおいて、日々多くの事例を扱っています。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












