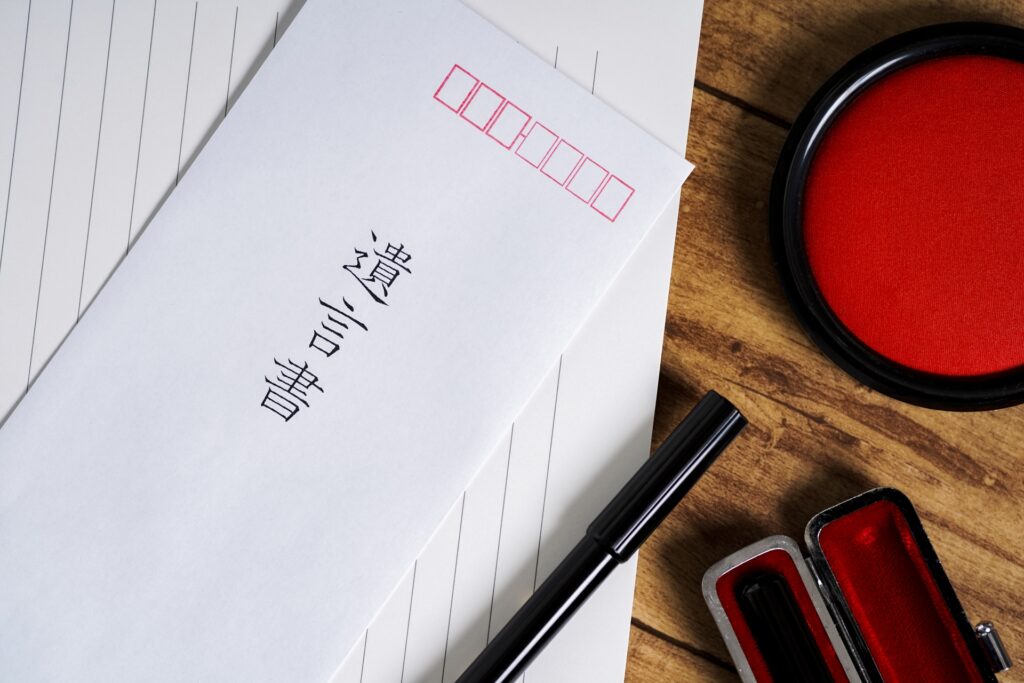
遺言書に記載することで法的効力を持つ「遺言事項」は民法その他の法律で決まっています。「遺言事項」以外の事柄を遺言書に書いても法的には無効ですが、全く意味がないわけではなく、「付言事項」のように将来の紛争防止に活用できるものもあります。
遺言書に書ける内容は決まっている?

どんな事柄でも、遺言書の中に書いておけば法的効力を持つのか―――というと、実はそうではありません。
遺言書の中に記載することで法的効力を持つものを「遺言事項」と言いますが、この「遺言事項」は民法その他の法律で決まっているのです。
「遺言事項」に当たらない事柄、例えば、「毎月命日には自分の好物だった鰻重を仏壇に供えること」とか、「松の木の剪定は年2回行うこと」といったことを記載しても、残念ながら法的効力がないため、相続人に強制的にそれらを守らせることはできません。
こうした「遺言事項」以外の事柄を遺言書に記載しても、その効力は法律的には無効です。
しかしながら、「遺言事項」以外の事柄を遺言書に記載してはいけないわけではなく、それらを記載したからといって遺言書全体が無効になるわけではありません。
むしろ、なぜそのような内容の遺言書にしたのか等を「付言事項」という形で記載しておくことで、相続発生後に相続人がその記載を読み、遺言者の心情を理解して、相続人間で争うことをやめる、といった事実上の影響もあるのです。
「遺言事項」とは

「遺言事項」とは、遺言書に記載することで法的効力を持つもののことです。
この「遺言事項」は、遺言内容を明らかにし、後日の紛争を防止するため、民法その他の法律で決められています。
「遺言事項」に当たるもの
遺言事項には、主に次のようなものがあります。
相続及び財産に関する事項

①相続分の指定
例えば、「妻Aの相続分を3分の1、子Bの相続分を3分の2とする」など、法定相続分と異なる割合で相続分を指定することです。
②遺産分割方法の指定
例えば、「自宅土地建物については売却したうえで、売却代金を法定相続分に従って分けること」、「不動産は妻Aが取得し、預貯金・株式は子Bが取得すること」など、分割方法を具体的に定めることです。
③相続させる旨の遺言
例えば、「不動産は妻Aに相続させ、預貯金・株式は子Bに相続させる」、「遺産は全て妻Aに相続させる」など、相続人に特定の財産を承継させる(あるいは包括的に承継させる)ことです。
④遺贈
例えば、「自動車を友人Cに遺贈する」など、相続人以外の者に対し、遺言をもって財産を取得させることです。
⑤特別受益の持戻しの免除
例えば、「これまでに子Bに対して行ってきた生前贈与による特別受益については、持ち戻しを全て免除する」といったように、本来であれば、遺産総額に持ち戻して計上すべき特別受益の持ち戻し計算をしなくてもよいと免除することです。
なお、法改正により、結婚して20年以上になる夫婦の一方から、他方の配偶者に対して居住用不動産を遺贈または贈与した時は、遺言書の中に持ち戻し免除に関する記載がなかったとしても、持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになっています。
身分に関する事項

①遺言による認知
例えば、「遺言者と●●●●(母親)との間に生まれた下記の子を自分の子として認知する」など、遺言をもって子を認知することです。
②推定相続人の廃除
例えば、「遺言者の子Bは、令和●年●月頃から遺言者の金品等の持ち出しを繰り返し、それを止めようとする遺言者に殴る蹴るの暴力をふるい、さらに令和●年●月頃からは、貸金業者から借りた借金の返済をしないまま行方不明となったため、遺言者がやむなくそれらの借金を返済するなど、遺言者に対する虐待や著しい非行があった。このため、遺言者は、子Bを推定相続人から廃除する」など、遺言をもって推定相続人を廃除することです。
遺言の執行に関する事項

遺言執行者の指定・執行権限の授与
例えば、「この遺言の遺言執行者として妻Aを指定する」、「遺言者は、遺言執行者に対して次の権限を授与する。(1)不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約および払い戻し(2)本遺言の執行に必要な場合に代理人および補助者を選任すること」など、遺言執行者を指定し、執行権限を授与することです。
その他の事項

①祭祀を主宰すべき者の指定
例えば、「遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として子Bを指定する」など、(お墓などの)祭祀承継者を指定することです。
②生命保険金の受取人の指定・変更
例えば、「下記生命保険の保険金の受取人を妻Bに変更する」など、遺言をもって生命保険金の受取人を変更したり、または指定したりすることです。
「遺言事項」以外のことを遺言書に書く場合

先に見たとおり、「遺言事項」以外の事柄を遺言書に記載しても、その効力は法律的には無効です。
しかしながら、「遺言事項」以外の事柄を遺言書に記載してはいけないわけではなく、それらを記載したからといって遺言書全体が無効になるわけではありません。
むしろ、「付言事項」という形で遺言者の思いを記載しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防止する効果が期待できる場合もあります。
「付言事項」が活用される場面で多いのは、遺言によって一部の相続人に法定相続分よりも多く(あるいは少なく)財産を取得させる場合に、その理由を記載したり、一部の相続人に対して遺留分侵害額請求権の行使を控えるようお願いしたりするものです。
以下、こうした「付言事項」の例を見てみましょう。
【一部の相続人の取得分が少ない理由】
「長男のDにはこの遺言であまり財産を残しませんでした。
Dに対しては、結婚後、浦和に自宅を新築する際に3000万円を援助したほか、経営する事業の損失補填として私から合計2500万円以上を出しましたので、もう十分だと考えたからです。Dはこのことをよく理解して、他の兄弟姉妹と争わないようにして下さい。」
【遺留分侵害額請求権の行使を控えて欲しい】
「今回、長女Eに多くの遺産を取らせましたが、これは、難病を抱えて思うように働けないEの今後を心配してのことです。母さんも、次女Fも、この点をよく理解して下さい。Eが安心して暮らしていけるように、2人とも、どうか遺留分の請求はしないよう切に願います。」
【家族にこれまでの感謝を伝える】
「私は、素晴らしい夫と子ども達、孫達に恵まれ、本当に幸せでした。足の悪い私に配慮して、行先を選びながら続けた年1回の家族旅行、本当に楽しかったです。みんなのおかげで、何不自由のない生活を送ることができました。本当にありがとう。私が旅立った後も、家族みんなで協力して平穏無事に暮らしていって下さい。」
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






