
離婚を考えている夫婦において、多くのケースで重要な問題となるのが経済的な問題です。厚労省の統計資料によれば、日本では1980年の専業主婦がいる家庭は1114万世帯で共働きという家庭は614万世帯だったところ、2022年には完全に比率が逆転し、専業主婦がいる家庭は539万世帯・共働きという家庭は1262万世帯となったそうです。共働きが増え、専業主婦が減ったとしても、夫婦間ではな収入格差がある場合も多く、その格差が特に大きい場合は離婚条件の設定において特別な考慮をすることもあります。そこで、今回は夫婦間で収入格差がある場合の離婚について、解説していきます。
収入格差が夫婦間で離婚するときの注意点

離婚のときに決めるべき事項
通常の離婚において決めるべき事項としては、
- 離婚するか否か
- (未成年の子がいる場合)親権者となる者の決定
- (未成熟子がいる場合)養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
が挙げられることが多いと思われます。このうち、夫婦(父母)の収入が離婚条件に影響を与える事項としては、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割だと考えられます。また、離婚前であれば婚姻費用も収入は算定の大きな要素ですので、影響が大きいものです。
今回の解説では上記の事項のうち、「婚姻費用・養育費」及び「財産分与」に注目して、説明をしていきます。
婚姻費用・養育費とは
婚姻費用とは、婚姻から生ずる費用のことであり、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用をいいます。衣食住の費用のほか、子の監護に要する費用なども含みます。
これに対して、養育費とは、離婚後子どもが成長・自立するまでに要する必要な費用のことです。
婚姻費用や養育費は、「標準的算定方式」といって、生活保持義務として義務者(支払う側)の収入を按分するという定型的な算定基準により夫婦・父母間で相当額を定めるというのが一般的です。
この標準的算定方式においては、給与所得者については2000万円を、自営業者については1409万円を上限として想定しており、これを超える収入を得ている場合は、公租公課その他の経費は自ずと一般的な基準を超えるものとして一律の算定ができないと考えられています。
高額所得者が義務者となる場合の婚姻費用の調整 方法①

上記各上限を超える収入があっても、それ以上の婚姻費用は認めない、という考え方です
婚姻費用においては、上限を超える部分は資産形成に当てられ、実際に費消するわけではないから、婚姻費用が上限なしにかかるというものではないという考えによるようです。
高額所得者が義務者となる場合の婚姻費用の調整 方法②
2つ目の調整方法としては、基礎収入の算定を調整するというものです。基礎収入というのは、いわゆる年収、額面での収入から、公租公課その他の経費を除いて計算するものですが、職業費や特別経費は高額所得者であっても必ずしも得る金額に比して高額化していくということは考えにくく、かたや公租公課の割合は高くなるので、基礎収入の割合は高額所得者の方が低く設定されています。
算定表上の基礎収入を導く割合(基礎収入割合)を、給与所得者の34%・自営業者の47%という設定よりもさらに低く設定して算定するという考え方です。
高額所得者が義務者となる場合の婚姻費用の調整 方法③

最後の調整方法は、基礎収入算定時に、公租公課等を考慮した基礎収入割合のほか、貯蓄率(総務省の統計による)を控除する、という考え方もあります。
高額所得者が当事者となる場合の養育費の調整
養育費に関しては、「子どもの成長・自立のための費用」であって、例えば学校教育のための費用などですから、高額所得者であったとしても上限なく増加するということが考えにくく、基本的には算定表の上限額をマックス値として考えるというのが一般的なようです。
仮にこの算定表上の上限では賄いきれないような事情がある場合には、当該費用について特別な事情があるとして通常の養育費に上乗せする、ということはあり得ます。例えば海外留学などの教育費といえるが通常のものではない費用が掛かる、という場合が考えられます。
婚姻費用・養育費についてのまとめ
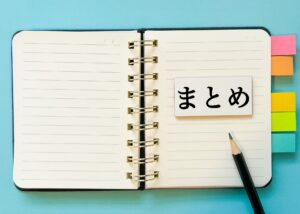
以上のとおり、基本的には高額所得者が婚姻費用や養育費の支払義務者となっている場合は、権利者たる監護者・親権者との収入も考慮しつつ、標準的算定方式の計算で額を決めることになるので、収入格差があればあるほどその相当額は大きくなるといえます。
しかし、婚姻費用の一部の説や、一般的な養育費に関しては、上限がないということはなく、算定表上の最大値が上限となることが想定されるという点は注意が必要です。
財産分与とは

財産分与とは、夫婦で築き上げた共有の財産を清算することであり、預貯金、不動産、保険、財形貯蓄、株式、退職金、車など、夫婦の財産を分けることです。
たとえ夫婦共働きではなく、片働きの場合でも、主婦(主夫)が家事・育児を行ったことによって、配偶者は稼働が可能になり収入を得ることができたと考えられるので、 財産分与は原則必要だと考えられています。
収入格差がある場合の財産分与
裁判所の原則的な考え方では、「結婚時」から「離婚成立 あるいは 別居時」までに得た財産を2分の1ずつ分けるべきとされています。たとえば夫婦のうちいずれかが主婦・主夫だった場合であっても、離婚に当たり決めるべき財産分与の割合が変わる、ということはあまりありません。これは専業主婦(専業主夫)であっても、基本的は家事や育児に従事し、夫婦の共同生活の維持や配偶者の所得活動による財産形成に寄与してきたといえるからです。
逆にいえば、所得活動をして財産分与をしなければいけない側の「個人の特殊な能力」や「努力」によって高額な資産形成がなされたという場合には、「財産形成に配偶者が寄与した」という見方は後退します。
寄与度において差が生じるとしていわゆる2分の1ルールを変更したケース①

夫が画家、妻が作家という夫婦において、各人が自分の財産を管理していたというケースでは、各人の預貯金や著作権を清算の対象とはせず、夫婦の共有財産を2分の1ずつで分け合う、ということをしませんでした。
寄与度において差が生じるとしていわゆる2分の1ルールを変更したケース②
航海士、海技士など、家庭ではほとんど過ごさず、大半の生活を海洋上で暮らし苛酷な状況で高収入を得る配偶者の場合、「そのような職務につかなくても得たであろう収入を超えた部分」について2分の1ルールを適用せずに、分与の割合を変更するという例があります。
財産分与についてのまとめ

以上のとおり、特別な資格や能力により一方配偶者が高収入を得ているという場合や、就労の態様により高収入を得ているという場合などは、収入格差によって財産分与の割合も変わってくるといえます。
ただし、その格差をどの程度考慮すべきか否かは、「一般的な収入として得られるであろうというレベルを相当超える財産形成をした場合」かどうかによって決まってくる、という点は注意が必要です。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






