
「相続放棄」をすると、多額の借金や売れない不動産などを相続しないことになりますが、結論として相続放棄ができない・認められない、いわば「失敗」してしまうということがあります。この記事では相続放棄の「失敗」について例を挙げて解説いたします。
そもそも相続放棄とは?
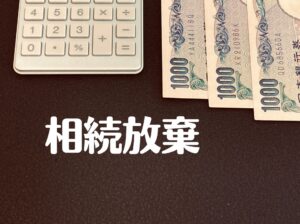
例えば、親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子は相続によって、親の財産のみならず借金も引き継ぐのが原則です。
こういったケースで子が親の残した借金から逃れるためには、「相続放棄」の手続が必要です。
相続放棄とは、字のとおり、相続する権利を放棄するということ。
相続放棄の手続を正しく完遂することができれば、上記のケースの子は、親の相続人ではなくなることになり、親の残した借金を引き継がないということになります。
ただし、親に何らかの財産(例えば自宅など)があった場合には、相続放棄をしてしまうと、この財産も相続することができません。
そのため、相続人は、相続放棄するべきかどうか、慎重に調査して考える必要があります。
ちなみに、上記のような「多額の借金」は典型的な相続放棄のケースですが、相続放棄をする理由・動機ついては特に限定されません。
「疎遠だから」「相続争いに巻き込まれたくないから」「生前に十分によくしてもらったから」などの理由でも相続放棄が可能です。
一方で、思いもよらない「落とし穴」にはまってしまい、相続放棄ができない・認められない、平たく言えば相続放棄が「失敗」してしまうことがあります。
相続放棄が失敗してしまうと、上記のケースでいえば、親の借金から逃れることができず、場合によっては自己破産なども考えなくてはならなくなる可能性があります。
以下では、相続放棄の失敗例をいくつか解説しますので、相続放棄をお考えの際には参考にして頂ければと思います。
相続放棄の失敗例
⑴ 手続きできる期間が過ぎてしまった!

相続放棄をする場合には、手続きの期限が存在します。
民法915条1項
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。…
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、ざっくり言うと、①被相続人が亡くなったことを知った、及び②自分が相続人だと知った、の2つを満たした時点です。
②については、多くの場合では①と同じタイミングになると思いますが、これがずれてくるケースもあります。
例えば、被相続人のお葬式には出たものの、被相続人の子(第1順位の相続人)がいるために、自分は相続人にはならないと考えていた被相続人のきょうだい(第3順位の相続人)について、先順位の相続人がみんな相続放棄したことを知ったタイミングなどが該当します。
上記のような例外はありますが、基本は「被相続人が亡くなってから3ヶ月」と覚えておいて頂ければ良いかと思います。
この期限までに相続放棄の手続を行わない場合には、「単純承認」といって、被相続人の権利義務を相続することを承認した、ということになってしまいます。
そうなると、もはや相続放棄はできなくなり、借金も含めて相続することになるということです。
「遺産に手をつけなければいつでも相続放棄できると思っていた…」「葬儀や遺品整理で忙しかったから…」「四十九日まではそっとしておこうと思ってそのまま忘れてしまった…」など、意外と熟慮期間を過ぎてしまうケースは多い様に思いますので是非ご注意ください。
⑵ 遺産を処分してしまった!

上記⑴で「単純承認」という言葉が出てきました。
民法では、こういった行動をした場合には単純承認をしたものとみなす、というものがいくつか定められています(民法921条)。
そのうちの典型的なものが、遺産の処分です。
遺産である現金を使ってしまった、預貯金を引き出した・解約した、というのが遺産を処分してしまったことに当たるというのは分かりやすいですが、例えば…
・被相続人名義だった車を売却した、名義変更をした
・被相続人名義の携帯電話を売却した、名義変更した
・被相続人の所有していた財産的価値のある物品(ブランド品など)を使用するつもりで自宅へ持ち帰った
というような行為も処分行為に当たるものと考えられます。
こういった遺産の処分があると、単純承認があったと判断され、相続放棄が失敗する可能性があります。
ちなみに、上記のようなケースでも、家庭裁判所が相続放棄を受理することがあります。
詳しくは省略しますが、家庭裁判所は「却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきである」と考えているからです。
これには(ある意味での)裏があり、実は、相続放棄の申立てが受理された場合でも、相続債権者などが後から相続放棄の有効・無効を争うことができるようになっているのです。
すなわち、例えば相続債権者は、相続放棄をした相続人を相手に「(被相続人の)借金を返しなさい」という訴訟を起こし、その訴訟のなかで、「相続人は遺産の処分を行っていたので、相続放棄は無効だ。だから相続人として借金を支払いなさい。」と主張することができます。
もし、この訴訟の中で遺産の処分が認められ、相続放棄が無効と判断されれば、相続人は借金の相続から逃れることができません。
このように、相続放棄ができるかどうか微妙な事案については、相続放棄の申立てが受理されたあとに争われる可能性がありますので、そもそも遺産の処分などの単純承認とみなされる行為をしないように気を付けましょう。
⑶ 家庭裁判所で手続きしなかった!

これもよくある勘違いなのですが、相続人や親族・遺族に対して、「私は遺産はいらない。相続を放棄する。」と宣言したり、遺産分割協議書にそういった内容を書きこんだりしたとしても、相続放棄の手続を行ったことにはなりません。
この記事で取り扱っている相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行ってする、法律上の意味での相続放棄です。
「相続放棄をしたのに、借金・滞納税金を支払えと言われて困っている。」というようなご相談がよくあるのですが、よくよくお話を伺ってみると、家庭裁判所で手続をしたことは無い(つまり相続放棄ができていない)という場合が少なくありません。
家庭裁判所で手続きをせず熟慮期間が過ぎてしまうと、単純承認があったものとみなされ、相続放棄はできなくなります。
3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをする。
繰り返しになってしまいますが、この原則を、特に覚えておいて頂ければと思います。
⑷ 借金の保証人になっていた!

これは、特に夫婦や親子で多いパターンなのですが、例えば夫名義の借金があるケースで夫が亡くなった場合に、相続人である妻が相続放棄をしたとします。
そうすると、夫名義の借金は相続しなくて済みますから、妻はその借金のことを放置しますよね。
しかしながら、妻がこの借金の保証人になっていたという場合には、保証人としての立場は何ら変わりがありません。
したがって、妻は、相続人としてではなく、保証人としてこの借金を弁済しなければなりません。
結果として、借金から逃れることはできませんので、その意味で相続放棄は失敗ということになります。
⑸ 次の相続が回ってきた!

これも、特に夫婦・親子で多いパターンなのですが、例えば夫名義の借金があるケースで、相続人として、妻と子どもがいたとします。
妻が相続放棄した場合には、妻は相続人では無くなり、借金から逃れます。
一方で、子どもが相続放棄の手続をとらなければ、子どもが唯一の相続人として借金を負うことになります。
子どもが借金を全て弁済できれば良いのですが、例えば子(孫)ができないうちに亡くなった場合には、相続人が第二順位である親(このケースだと母親)になるということがあり得ます。
そうすると、一度は子どもが相続した(元々は)夫の借金について、今度は子どもからの相続として、妻に再び回ってくるということがあり得ます。
この場合には、冷静に、夫の相続に引き続き、子どもの相続についても相続放棄の手続きをする必要がでてきますので注意が必要です。
また別のパターンとして、上記⑷のように夫名義の借金について妻が保証人になっていた場合には、子どもは父母の両方の相続について相続放棄しなければ、借金そのものと保証人としての債務の両方から逃れることができません。
このように、一つの借金から逃れるために複数の相続放棄が必要となる場合もありますから、慎重に相続放棄の有無の検討が必要になります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
相続放棄というのは、簡単なようで、意外と「落とし穴」にはまって「失敗」してしまうということが多々あります。
慎重にひとつひとつ時間をかけて確認できれば良いのですが、いかんせん「3ヶ月」という熟慮期間の制限がありますので、のんびりはしていられません。
もし相続放棄の可能性があるのであれば、できる限り早い段階で(できるのであれば被相続人が亡くなって相続が発生してしまう前に)、一度弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。
相続放棄についての詳しい解説はこちらもご参照ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






