
不正競争防止法とは、企業間の不適切な競争を防ぎ公正な競争を維持することを図るための法律であります。
その内、第2条1項21号では、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(いわゆる営業誹謗行為」を「不正競争」行為と位置づけ、規制しております。
他社からの行為が「営業誹謗行為」に該当するのではないかと思いつつも、指摘を躊躇してしまった結果、企業の利益に影響する場合もございます。
本ページはどのような行為が「営業誹謗行為」に該当するのか、「営業誹謗行為」に対して警告をする際に注意すべき点について専門家が解説するページとなっております。
営業誹謗行為の要件
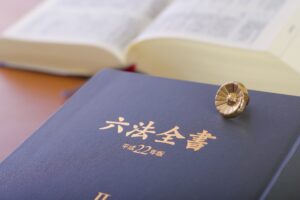
不正競争競争防止法第2条1項21号は、企業にとって重要な資産である営業上の信用を虚偽の事実をあげて害することによって、競業者を不利な立場に置くことを通じて、自ら競争上有利な立場に立とうする行為を「営業誹謗行為」として規制しております。
営業誹謗行為に該当する要件は、以下の5つによって構成されております。
- 競争関係にある
- 他人の
- 営業上の信用を害する
- 虚偽の事実を
- 告知し、又は流布すること
次に、各要件について簡単に解説いたします。
1 競争関係にある

実際に、特定の販売競争などの競争が生じていることに限られるものではなく、双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる、と考えられています。
また、広く同種の商品を扱うような業務関係にあればよく、現実に競争関係が存在していなくとも、市場において競合が生じるおそれ、つまり将来の潜在的な競争関係があればよいと考えられています。
2 他人

特定の他人である必要があり、ある業界全体について信用を毀損することを主張したとしても、「他人」には該当しません。
3 営業上の信用を害する

営業活動に関する経済的な社会的信用を「営業上の信用」と言います。
例えば、商品の性能、営業者の支払い能力、営業能力の評価などを含みます。
また、「営業」は、営利を目的とする事業だけでなく、非営利事業(学校、病院、学術研究など)も含まれます。
「害する」とは、信用を低下させるおそれのある行為を指し、現実に信用が低下することまでは求められておりません。
4 虚偽の事実

客観的に事実と反する事実を「虚偽の事実」にあたり、告知者・流布者が虚偽だと思い込んでも、結果的に真実であれば営業誹謗行為には該当しません。
他方で、告知者・流布者が真実と信じていたとしても、結果的に虚偽であれば営業誹謗行為に該当してしまいます。
また、「事実」の告知や流布については、事実を断定しなくとも、「~かもしれない」「~のようである」といった推測的な表現であっても、信用毀損行為に該当する場合があります。
過去の裁判例では、「虚偽の事実」について以下のような判断もしております。
「信用を害する虚偽の事実」とは、証拠等をもって該当性の有無が判断できるような客観的な事項をいうものであって、証拠等による証明になじまない価値判断や評価に関する記述を含まないとし、そのような記述は、意見ないし論評の表明として、市場における自由な競争行為の一環として許容される。(東京地裁平成17年1月20日判決)
5 告知し、又は流布すること

特定の人に対する伝達のことを「告知」といいます。
例えば、競業会社の取引先に個別に伝えた場合、告知にあたります。
不特定多数に虚偽の事実を伝える行為のことを「流布」といいます。
インターネットへの掲載、新聞やテレビの広告、雑誌などの記事による場合、流布にあたります。
この告知や流布は、被害者の信用=他者からの評価を害することに向けられる必要があるため、他者に対してなされる必要があります。
実際の裁判例

以下では、実際に営業誹謗行為が問題となった裁判例について説明いたします。
1 東京地裁平成27年9月29日判決
畳の塗料の販売をする原告のタタミ染め製品には欠陥がないにもかかわらず、アパートの賃貸業や清掃業を行なう被告が、同製品には欠陥があるなどとして同製品の販売店に対して虚偽の内容を記載した書面を配布した事案。
裁判所は、配布先の販売店が同製品の取扱いを停止したものの、苦情申立て等がなかった場合に見込まれる本件製品の売上高が不明であるとして逸失利益の請求は認めなかったものの、被告の行為の悪質さ等に鑑み400万円の損害賠償を認めた。
2 大阪地裁昭和60年5月29日判決
被告は、自己の実用新案権を侵害するとして、原告の製品の販売中止を求める警告書を原告の取引先に配布した事案。
裁判所は、上記行為が信用毀損行為に該当するとして、裁判所は、原告に対し、日本経済新聞、日経産業新聞及び日刊工業新聞の各全国版に各1回ずつ掲載するよう命じた。
まとめ

他社による営業誹謗行為を注意する際、「実質として競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先の取ないし市場での競争において優位に立つこと」を目的としていることを告知、流布の形式、文面のみならず、経緯、配布先、その他の事情を盛り込んで営業誹謗行為に該当することを指摘する必要があります。
今後、他社からの行為が営業誹謗行為に当たるのではないかと思った際には、先ほどご説明したことを参考に警告等をご検討いただけると、企業の信用価値の維持といったメリットがございます。






